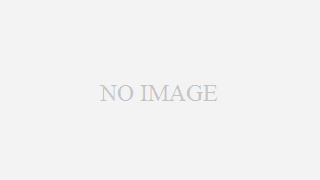 相続
相続 【大阪で所有者不明不動産を放置しないために|行政書士が行う相続土地国庫帰属制度活用と事前整理の完全ガイド】第1章-大阪で急増する「所有者不明不動産」とは何か
「親名義のままの土地がある」「山林や遠方の土地を相続したが使い道がない」「相続人が多くて話し合いが進まない」こうしたご相談は、大阪でも年々増えています。特に近年は、相続土地国庫帰属制度が始まったことで「国に返す」という選択肢が現実的になりま...
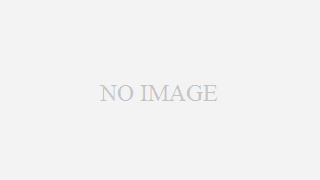 相続
相続 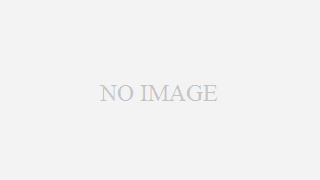 相続
相続 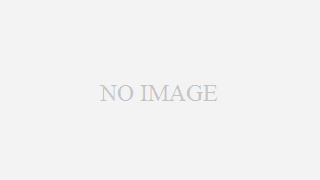 家系図
家系図 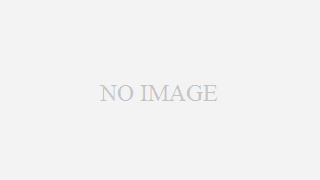 家系図
家系図 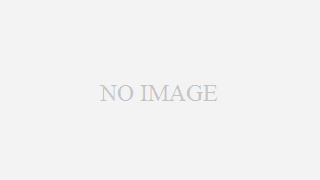 家系図
家系図 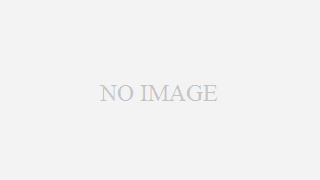 家系図
家系図  民泊
民泊  相続
相続  民泊
民泊 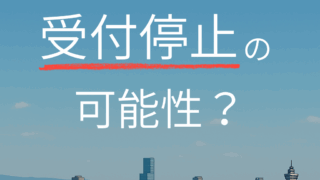 民泊
民泊