相続手続きに必要な「戸籍」とは?【基本知識と種類を解説】
相続における戸籍とは?どんな場面で必要になるのか
相続手続きを始めると、まず直面するのが「戸籍集め」です。
銀行口座の解約、不動産の名義変更、保険金の請求など、ほとんどすべての相続関連手続きで戸籍の提出が求められます。
私も実務で多くのご相談を受けていますが、「なぜこんなに戸籍が必要なのか?」「こんなに大変だとは思わなかった」という声をよく耳にします。
それほど、戸籍集めは相続手続きの第一関門と言えるでしょう。
なぜ相続手続きに戸籍が必要なのか?【法的根拠と実務】
相続では「誰が相続人であるか」を法律的に証明しなければなりません。
たとえば、被相続人(亡くなった方)に隠し子がいた場合など、本来の相続人の範囲が大きく変わるためです。
相続人の範囲は日本の法律(民法)で定められています。
そのため、金融機関や法務局も、「戸籍で確認できない相続人は認めない」というスタンスを取っています。
特に、戦前の戸籍が絡むと漢字が旧字体で読みづらく、調査に時間がかかることもあります。
相続手続きで集める戸籍の範囲とは?【出生から死亡まで】
相続手続きでは、単に「亡くなった時点の戸籍」だけでは足りません。
必要なのは、被相続人が生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍です。
これを「出生から死亡までの戸籍」と呼びます。
理由は、相続人を漏れなく確定するため。
たとえば、被相続人が結婚・離婚・再婚していた場合、それぞれの戸籍に相続に影響する事実(子の出生など)が記載されています。
私が知る事案でも、戸籍をたどった結果、依頼者自身も知らなかった異母兄弟が判明し、相続人の範囲が広がったことがありました。
このように、戸籍を丁寧に集めることが、円満な相続の第一歩なのです。
必要な戸籍の種類とそれぞれの役割とは
相続手続きで必要な戸籍には、以下の種類があります。
- 戸籍謄本:現在有効な戸籍全体の写し
- 除籍謄本:結婚・死亡などで除籍された戸籍の写し
- 改製原戸籍:法改正などで作り直される前の古い戸籍
これらをすべて揃えないと、相続人の特定に穴が生じる可能性があり、金融機関や役所から受理されません。
特に注意すべきは、改製原戸籍。
1947年や1980年代に戸籍法が大きく改正された影響で、それ以前の古い情報は改製原戸籍にしか残っていないことが多いのです。
戸籍を取得する方法と注意すべきポイント
戸籍は、基本的に本籍地の市区町村役場で取得します。
遠方の場合でも、戸籍証明書等の広域交付制度により、近くの役所ですべての戸籍を請求することが可能となりましたが。その場合、請求できる人の制限などがある(代理人、郵送請求では不可など)為、細かな注意点があります。
また、古い本籍地がどこかわからない場合や、複数回本籍変更があった場合には、追跡調査が必要になることも。
私自身もサポート業務で、過去5回本籍地が移転していたケースに直面しましたが、各地役所へ問い合わせながら地道に調べました。
焦らず、一つひとつの戸籍を確実に取得することが、相続手続き成功のカギです。
まとめ
相続手続きにおいて戸籍は、単なる「書類」ではなく、相続人を確定し、法的に手続きを完結させるための不可欠な存在です。
生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集め、抜け漏れのないように進めることが、スムーズな相続の第一歩。
もし戸籍集めに不安を感じたら、早めに専門家に相談することも検討しましょう。



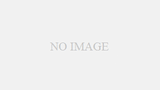
コメント