戸籍収集の注意点とスムーズな手続きのコツ
相続の戸籍集めで起きやすいトラブルとは?
相続手続きに必要な戸籍は、実際に集め始めてみると想像以上に複雑です。
私が支援してきた中でも、特に多いトラブルは次の3つです:
- 戸籍が集めきれていなかった(見落とし)
- 古い戸籍が手に入らない・時間がかかる
- 読み方がわからず、解釈を誤ってしまう
戸籍収集の最大の難点は、「被相続人の本籍地が複数あったり、転籍を繰り返していたりする場合」です。
中には5〜6か所の自治体に請求を出す必要があるケースもあり、1通の除籍謄本を取得するだけで2〜3週間かかることも。
戸籍収集の遅延がそのまま相続手続き全体の遅れにつながります。
旧字体や手書き戸籍の「読めない問題」にどう対処するか
特に戦前に作られた戸籍では、「読めない」という問題も発生します。
手書きで書かれていたり、漢字が旧字体や略字で記されていたりするため、現代人には判読困難です。
たとえば「吉(下が長い)」や「齋藤(斉藤)」など、見慣れない漢字が登場するため、「別人の戸籍かもしれない」と不安になる方も多いです。
私も実際に、依頼者が間違って“同姓同名”の全く別の人物の戸籍を取り寄せてしまったことがありました。
こうした場面では、自治体の窓口に確認を入れたり、行政書士などの専門家に内容の読み解きを依頼するのが得策です。
プロであれば、旧字体でも解読可能なスキルと経験がありますし、誤った手続きのリスクを最小限に抑えることができます。
専門家への依頼は必要?代理取得のメリットと選び方
戸籍収集は基本的に本人または法定相続人であれば可能ですが、実務的には行政書士などの専門家に依頼するメリットが大きいです。
具体的には以下のメリットがあります:
- 本籍地の追跡調査を代行してくれる
- 不備があった場合の再請求も任せられる
- 手続きの時間・労力を大幅に軽減できる
特に、仕事が忙しい方、高齢で体力に不安のある方、遠方にお住まいの方には心強い存在です。
私も過去に「自分でやろうとして3ヶ月かかっていたけれど、専門家に任せたら2週間で終わった」と感謝された経験があります。
ただし、依頼する際は「相続業務に強い専門家」であることを確認しましょう。
資格だけでなく、相続実務の経験値があるかがカギになります。
相続人が遠方にいる場合の効率的な進め方
相続人が全国に散らばっているケースも珍しくありません。
その場合、郵送やオンライン手続きを最大限活用することが重要です。
現在では多くの自治体が、郵送での戸籍請求に対応しており、必要書類や記入方法は各市区町村の公式サイトで確認できます。
マイナンバーカードを使って、一部の手続きをオンラインで行える自治体も増えています。
2024年3月1日戸籍法改正により利便性が向上した戸籍証明書等の広域交付制度を活用することも有効です。
失敗しないために押さえておきたい3つのポイント
最後に、相続の戸籍収集を失敗しないために、特に大切なポイントを3つご紹介します。
- できるだけ早く取りかかること
→ 戸籍取得には想像以上に時間がかかります。葬儀が落ち着いたらすぐに始めましょう。 - チェックリストを作って記録を残すこと
→ どの戸籍を、どこから、いつ請求したかを整理しておくと混乱しません。 - 迷ったら早めに専門家に相談すること
→ 手間やストレスを大幅に減らし、スムーズな手続きが実現できます。
まとめ
戸籍の収集は、相続手続きの中でも最も時間と労力がかかる部分です。
トラブルや遅延を防ぐためには、早めの準備、情報の整理、そして場合によっては専門家の力を借りることが大切です。
私自身、数多くの現場を見てきましたが、共通して言えるのは「準備の早さが、相続手続きの成否を左右する」ということ。
この記事を参考に、ぜひ安心・円滑な相続を実現してください。


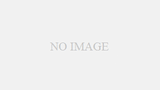
コメント