【2025年最新版】法定相続人とは?相続の基本を行政書士が解説
相続が発生したとき、まず初めに確認しなければならないのが「法定相続人」です。
法定相続人とは、法律(民法)によって定められた、遺産を受け取る権利を持つ人のことを指します。
相続手続きの第一歩は「誰が相続人なのか」を正確に把握することから始まります。
行政書士として多数の相続相談を受けてきた経験から言えるのは、この基本を知らずにトラブルに発展するケースが非常に多いということです。
法定相続人とは?民法で定められた「相続の担い手」
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の死亡と同時に、法律上自動的に相続権を取得する人たちです。
この相続権は、遺言がない場合の遺産分割協議や、相続登記の際に非常に重要な役割を果たします。
民法では、法定相続人の範囲と優先順位が細かく定められています。
配偶者は常に相続人|他の相続人と順位の関係
まず大前提として、配偶者(法律上の婚姻関係がある妻または夫)は常に法定相続人になります。
たとえ別居していても、婚姻関係が解消されていなければ相続権があります。
ただし、配偶者が相続する割合(法定相続分)は、他に相続人が誰であるかによって変動します。
たとえば、配偶者と子がいる場合は、それぞれ1/2ずつ。
一方、子がいない場合は、被相続人の父母や兄弟姉妹と分け合うことになります。
子ども・父母・兄弟姉妹の相続順位とは
配偶者以外の法定相続人は、以下のような順位で決まります。
第1順位:子(直系卑属)
子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が「代襲相続」します。
第2順位:父母(直系尊属)
子がいない場合、父母が相続人になります。祖父母が該当することもあります。
第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいないときに兄弟姉妹が相続人になります。兄弟が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります。
この順位は厳格で、たとえば第1順位に該当者がいる場合は、第2・第3順位の人は相続権を持ちません。
相続放棄・廃除・代襲相続など注意すべき特殊ケース
実務上で注意が必要なのが、「相続放棄」や「廃除」、そして「代襲相続」です。
たとえば、相続放棄をした相続人がいると、その人は最初から相続人でなかったものとされます。
その場合、次の順位の人が法定相続人になります。
また、被相続人の生前に虐待などの理由で相続権を「廃除」されているケースや、前述の通り、既に亡くなっている子の子が相続する「代襲相続」も頻繁に出てくる論点です。
実務でよくある相談|再婚・連れ子・認知された子の相続
実際に多くのご相談を受けるのが、「再婚後の家族構成に関する相続」です。
たとえば、連れ子は被相続人が正式に養子縁組していない場合、法定相続人にはなりません。
また、認知された非嫡出子(婚外子)については、近年の法改正により、嫡出子と同等の相続権を持つようになりました。
このようなケースは、家族構成や戸籍関係の調査をしっかりと行わなければ、後々大きなトラブルを招く可能性があります。
私自身、こうした家族背景が複雑な相続案件を数多くサポートしてきましたが、事前に「誰が法定相続人か」を明確にしておくことが、相続問題を防ぐ最大の予防策になります。
まとめ
相続は、法律だけでなく人間関係が深く絡む非常にデリケートな問題です。
だからこそ、「正しい知識」と「早めの対策」が不可欠です。
次章では、法定相続人が関わる実務と、相続分の計算、トラブル回避のポイントを詳しく解説します。


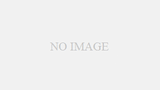
コメント